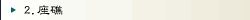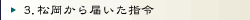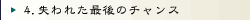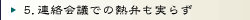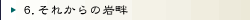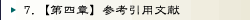1.三国同盟と松岡洋右
―近衛を避けた松岡―
1941年4月22日、外務大臣・松岡洋右を乗せた陸軍機が立川飛行場に着陸した。ヒトラー、ムッソリーニ、スターリンといった国際政治の主役たちとの会見を終えての凱旋であった。しかも、日ソ不可侵条約という大きな手土産もある。
飛行場に通じる沿道には、一目、今をときめく大政治家を見ようと、多くの群集が押し寄せていた。そんな騒ぎの中、飛行場に総理大臣・近衛文麿の姿もあった。
閣議で、閣僚は迎えに出ないと申し合わせたにもかかわらず、立川までやって来た近衛の胸中は察するに余りあった。
「総理である自分が立川まで直々に迎えに出れば、いかに苛烈な松岡といえどもその心を少しは和らげてくれるのではないか」
五摂家筆頭という名門に生まれ育った近衛としては最大級の配慮であった。松岡がへそを曲げれば、どうなるかを知っていた 近衛としては居ても立ってもいられなかったようである。
しかし、近衛の希望的観測は無惨にうち砕かれた。
タラップを降りた松岡は、首相専用車に乗るよう誘う近衛を振り払うと、外務省差し回しの車に大橋事務次官と乗りこんでしまった。一説によれば、握手を求め た近衛に、松岡は右手に大げさに巻いた包帯を誇示するかのようにぞんざいな態度で左手を差し出し、近衛は気分をいたく害したという。右手の傷は、モスクワ 駅頭でスターリンの出迎えを受けた時に負ったという擦過傷だった。(※1)松岡にとっては名誉の負傷だったのかもしれない。
わざわざ立川まで歓迎に出向いた首相近衛は、あっさり袖にされてしまった。
この1件に関しても、関係者が伝える諸説は細部で一致しないが、共通項だけとれば、松岡が近衛との車に同乗することを巧妙に避けたことは間違いないようである。
近衛には、松岡との同乗を忌避する理由は何もない。では、何故、松岡は避けたのか。
この事実は、立川に降り立った時点で松岡は既に「日米諒解案」に関してかなりのレベルの情報を得ていたと考えなければ理解できない。
事務次官大橋の証言では、立川からの車中、「日米諒解案」の話を聞いた松岡は開口一番、「それは僕がスタインハートに言った話ではないんだな」と言ったことになっている。(※2)
この証言に従えば、松岡は、帰国して大橋から話を聞くまでは、モスクワで自分が米国大使スタインハートに対して行った提案に対する回答が日本に届いたものと思っていたということになる。
しかし、もし松岡がこの時点までそう思っていたとすれば、当時の外務省は外遊中の外相に留守中に起こった重大事をも連絡する術がなかったということになる。そんなお粗末な話があるだろうか?
「スタインハートへの提案」とは、モスクワを訪問した松岡が、アメリカの駐ソ大使スタインハートに提案した日米関係打開に向けた首脳会談のことである。
しかし、自分がまだ帰国もしないうちに回答を返してくるほど、アメリカがせっかちだとでも松岡は思っていたのであろうか。
どう考えても、日本に帰ってくるまで松岡が日米諒解案のことを知らなかったというのは不合理な話である。松岡が大陸に居る間に、ことの次第は既に報告されていたと考えた方が合理的である。
実際、列車がソ満国境をさしかかる頃に「諒解案」に関して最初の報告を受け、対米外交を野村に先を越されたと思った松岡は、大連で2日間ふて寝していたという詰も伝わっている。(※3)
当時、外務省内部は、日米国交回復を3国同盟に優先して推進しようとする寺崎アメリカ局長と、それに対抗してあくまで3国同盟に固執しアメリカに対して対 決姿勢で臨もうという松岡を頂点とした大橋事務次官、加瀬俊一秘書官らの2つの勢力に分かれていたという。(※4)
日米諒解案を親独政策を推進する自分に対する嫌がらせ、あるいは謀略ととった松岡としては、事態を把握する前にむざむざ敵の術中に陥るのを防ぐため、近衛との同乗を拒んだのであろう。
その後、立川を後にした松岡は、首相官邸を目前に、車の行き先を宮城へと転じさせた。
これには、松岡が宮城遥拝を言い出したのは飛行場でのことであり、そうした芝居じみた行為を嫌った近衛の方から同じ車に乗るのを断ったという説もある。
いずれにしても、松岡の帰朝を歓迎し、日米諒解案を承認させようと、首相官邸で待ち受けていた閣僚たちは待ちぼうけを食わされることになった。
嫌がらせとしてそうしただけではなく、帰国したばかりの松岡には状況を把握するために時間が必要であったことは間違いない。宮城遥拝を済ませた松岡は、今度は外務省へ回った。外務省職員の「歓迎会」に出席するという口実だった。
外務省に入った松岡は、訪欧にも同行した腹心の部下・加瀬俊一に命じ、「日米諒解案」の条文検討を行わせたという。検討の結果、
「日米諒解案は3国同盟を去勢するためのものである」と加瀬は報告したという。(※5)
少なくとも岩畔の意図は正しく理解されたようである。
しかし、松岡にとっても加瀬にとってもそれは許すことのできない謀略だった。