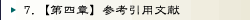6.それからの岩畔
東条によって南部仏印に飛ばされた岩畔は、開戦とともにマレー半島を南下する。
「該博な科学知識とその非凡な応用」は、「万物ことごとくこれを戦力化しないではおかないという闘魂」とともに、「部下をして創意工夫の意欲を大いに盛り上がらせた」という。(※10)
東南アジアの水田が、日本の田とは土壌の質も異なり、徒歩前進に支障のないことを自ら確かめた岩畔は直線ルートの進撃を指示したというのである。
「水田、田にあらず」と「全軍を叱咤激励」し「破竹の進撃を」可能ならしめたという。
快進撃を果たした連隊だったが、半島先端部付近で彼自身が貫通銃創を負い、シンガポールでの療養生活を余儀なくされた。
その後、傷の癒えた岩畔に与えられた使命は、インド独立工作だった。
以前から、日本が対英謀略として行ってきたインド独立運動を引き継げというのである。
インド独立工作のための岩畔機関が設立された。
それまでの「インド謀略計画」は「インド施策計画」として国家レベルの施策に格上げされ、莫大な予算と人員を獲得した。
岩畔機関は、数十名の陸海軍軍人、外務官吏、インドに関わりの深かった企業、国会議員などから構成され、盛時5百名の機関員を誇ったという。(※11)
機関設立に当たって、面白いエピソードがある。
犬養毅元首相の子息である犬養健から、インドの一地方の王の娘と会ってくれと頼まれた岩畔は、王家の紋章入りの招待状を受けとると上海キャセイホテルに彼女を訪ねた。
やがて憤然とホテルを後にした岩畔は、後にこう語っている。
「何のことはない淫売なんですよ。そういう(碌でもない)ことを犬養がやっておるんです」
(岩畔豪雄氏談話速記録より)
工作には莫大な資金が投下される。さまざまの思惑の人士が群がったようである。
かくして発足した岩畔機関は、サイゴンからの宣伝放送、潜水艦を使った独立軍部隊のインド国内潜入など活発な活動を行い、ニューデリーの敵側謀略放送が岩畔大佐を名指しで揶揄するほどだったという。
しかし、インド国民軍の自主性を尊重する岩畔の方針は、あくまで独立軍を日本の戦力として使おうという大本営の方針には合わなかった。
やがて、南方総軍司令官のもとに、「岩畔のインド人に対する取り扱いは野放図にすぎるぞ」との東条の苦情が届いた。(※12)
大本営とインド国民軍の板挟みとなった岩畔は、その挙げ句、機関長の座を追われる。
インド独立工作を外された岩畔は、その後スマトラの軍政を経て、地獄と形容されたインパール作戦に従事する。
それは、日本陸軍に於ける狂気にも近い精神主義の横行を如実に示すような作戦であった。
牟田口廉也の発案になり、「誰が考えても勝てる気遣いなどなかった」と岩畔が言うように、まともな作戦ではなかった。
南方総軍もビルマ方面軍も、「とんでもない」と、反対したこの作戦を実現したのは、東条とそれを支える陸軍大学軍刀組のエリート参謀たちであった。この 頃、既に人気のなくなっていた東条としては、ここで多少頑張れば少しは人気が出るのではないかと考えていたというのである。
悲惨な結果となったインパール作戦だったが、十重二十重(とえはたえ)に包囲されたペグ一山系から、敵陣を突破し部隊を無事脱出させたことは、岩畔にとっても武人としての誉れであったろう。
苛烈を極める前線にあって、彼のポケットには常に自然科学書と易経がしのばせてあったという。
作戦の合間に取り出しては読み、「夜は、星座を眺め天体の動きを凝視して深い思索に耽っていた」という(浅野祐吾氏)。
驚くべき事に、彼はこの頃から既に、
「今次大戦は原子爆弾によって終結するであろう」
と、側近幕僚に予言していた(浅野氏)。
―従軍慰安婦―
「変な話ですが、慰安婦という女がいるのです」
その談話速記録の中で岩畔は過酷な行軍についてきた従軍慰安婦のことを語っている。
インパール作戦を前に、慰安婦と病人を後方に下げるよう要請した岩畔だったが、司令部からあっさり断られたという。
かつて小大臣と呼ばれた岩畔も、女や病人を前線から下げる力さえ失っていた。
仕方なく、将校の予備の軍服を彼女たちに着せたという。
しかし、部隊が逃げ込んだビルマ山中の行軍は苛酷だった。隊列を横切る象の群に踏まれて命を失った慰安婦もいた。後続の岩畔が現場にさしかかった時には既に白木の墓が建てられていた。
やがて、篭城戦に終止符を打ち、みごとにペグ一山を脱出した岩畔が耳にしたのは終戦の報らせだった。
次の指令が与えられた。
単身、東京に戻れと言うのである。
軍務局長の内命であった。
岩畔は、単機、東京に向かった。
この時彼を迎えたのが4年前、南部仏印に出征する時、東京駅に見送りに来ていた佐藤裕雄大佐であった。
軍務局長の内命は出ていたものの、陸軍はもう無かった。
―戦後の岩畔―
その後の岩畔の経歴は長く空白である。
東京裁判では、証人として出廷を要請されたものの、彼自身が戦犯として訴追されることはなかった。
京都産業大学の須藤眞志教授はそれを、「アメリカが岩畔の努力を高く評価していたからである」としている。(※13)
その後の長い人生を、岩畔は哲学と思索に没頭して過ごした。
「日本は物量だけでなく、哲学の面でもアメリカに既に負けていたのではないか」
岩畔にとって、悲劇を2度と繰り返さぬためには、新しい哲学の確立こそ急務と考えたようだ。
彼は長年の思索生活の成果を『戦争史論』と『科学時代から人間の時代へ』という2冊の本をはじめとした、5千余枚の論文に書き留めた。
昭和40年、京都産業大学世界平和研究所長という職を得た岩畔は、その後も同様の思索生活を続けた。
その間には、来日したイギリスの哲学者アーノルド・トゥインビーとの対談に心を弾ませたこともあった。
世界の碩学アーノルド・トゥインビーをして、
「日本訪問中の多くの討論会や会合のうちで、この討論が最も興味深く、得るところが大きかった」
と言わしめたのは、岩畔の実体験に裏打ちされた「哲学」のゆえだったのであろう。
その後もトゥインピーとの手紙のやりとりは続き、遺稿ともなった著書『科学時代から人間の時代へ』には、トゥインピーからの寄稿も得ている。
かくして、岩畔豪雄の激動と静謐の人生がその幕を閉じたのは、昭和45年11月22日のことだった。
享年73歳であった。