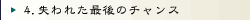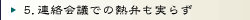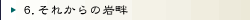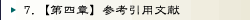3.松岡から届いた指令
電話での松岡の態度からある程度の予想はついていたものの、野村、岩畔、井川、陸海両軍の駐在武官の焦燥をよそに回答はなかなか返ってこなかった。
しかし、5月3日に届いた松岡の電報は野村を仰天させた。それは日米諒解案に対する返電ではなく、あろうことかアメリカを洞喝せよという指示であった。
「ヒトラー、ムッソリーニらはヨーロッパ大戦における勝利を既に確信している。日本も独伊を裏切ることはない。今、アメリカがイギリスに味方して参戦して もそれは戦争をいたずらに長引かせるだけであり、世界文明の荒廃を招くだけである。自重を求める」
ハルにそう通告しろというのである。
また、それに追加して、何を思ったのか「日米中立条約」をアメリカに提案しろというのである。
日米諒解案に回答もしないうちから、別の提案を持って行けということである。ほとんど支離滅裂な単なる嫌がらせだった。
松岡の尋常ならざる神経は、彼をして見境のつかない状態にしていた。
野村は役目上仕方なくハルのもとを訪れた。
野村はまず日本政府からの提案として、日米中立条約を提案した。
それに対してハルは、
「それは4月9日の文書で述べている提案とは全く別の問題である」
とあっさり退けた。そんなことより諒解案に対する返事を早くしろというのである。(※6)
野村としても、ハルに提案を退けてもらえばそれが一番だった。
また、例の恫喝的言辞に関しては、「松岡から電報が来ているが、これにはいろいろよくないことも書いてある。お渡ししますか」と尋ねる野村に、ハルは、「良くないことが書いてあるのだったら、そちらにとっておいてもらえば結構」と答えたという。
実際のところ、ハルは日本の外交暗号を解読し、その電文の内容を既に知っていたが、そんなことは野村も知りようがなかった。
松岡から「日米諒解案」に対する回答が届いたのは、請訓電打電の実に24日後のことであった。しかし、それは岩畔らが待ちに待った返事ではなかった。
松岡は、ヒトラーの意見を取り入れた、最初のものとは似ても似つかぬ、新たな「諒解案」を送ってきた。
日米双方の思惑を縦糸、横糸として巧みに織り交ぜた岩畔、ドラウトの苦心の跡は片鱗も残されていなかった。
話し合いの当初の段階から、この間題が取り上げられるなら、交渉を続けることはできないとまでアメリカ側が言い切っていた 「日米共同しての独英戦争調停」も条文としてはっきりとうたわれていた。
また、日米諒解案で3国同盟の発動に関して、
「ドイツが積極的に攻撃された場合にのみ(only when)」
とうたい、暗にアメリカが自衛権の発動として参戦した場合には3国同盟は発動しないというニュアンスを持たせた部分も消え去っていた。
松岡案を一目見たウォーカーは、
「そもそも国際間の妥協も男女の仲のようなもので、もし成立させようとするなら相当の魅力をもって口説かなければならない。これではまるで道心堅固な老尼僧のようではないか」と嘆いた。(※7)
「政治家の魂を込めた絵画は、法律家の用器画に変わってしまった」(※8)
アメリカ側は、松岡作の「諒解案」を受け取ると暫くの間、それについて一切のコメントを発しなかった。
ひたすら沈黙を守るアメリカに対して、野村や岩畔としてはともかく話し合いの努力を続けるしかなかった。
―ハルが示した親愛の情―
野村−ハル会談の大部分はワードマンパークホテルのアパート棟にあるハルの居室で行われた。アメリカからは通訳としてバレンタインが、日本からは5月中旬から6月下旬までの間、岩畔、井川が同席した。
アメリカ国務長官と、これまた一国の大使がこうした私的な場所で会談するということ自体極めて異例なことである。
すべては、松岡によって「日米諒解案」が葬り去られた結果、日米交渉が私生児の状態に止まったためであるが、その後、方針を徐々に変えていくアメリカにとって、事が公けになっていないことは、結果的ではあるが、きわめて好都合であった。
野村、井川、岩畔の3人は、毎回、夕刻にハル邸を訪れ、夫人の愛想の良い出迎えを受け書斎へ通された。
途中でお茶の時間もはさみ、和気あいあいとした雰囲気の中で会談は進められた。終わるのは夜の9時から10時頃であった。
3人の中で、ハルは、岩畔にことさら親愛の情を示したという。
野村、井川とともに初めてハル邸を訪問した岩畔に、ハルは、自分がくつろぐために愛用している赤い革張りの椅子をすすめ、それ以後、その椅子は岩畔の専用になった。
会談中も、ハルは、岩畔の発言にはいつも微笑みながらうなずいたという。
岩畔は、ハルが自分に対してことさらに示す「親愛の情」を、「私が日本陸軍の代弁者であると見たことと、70歳を超えているハル長官から見れば44歳の私が子供っぽく見えたため」と分析している。
児島裏著の『開戦前夜』でも、「静かで正直で自信にあふれた人物」という、ハルの岩畔に対する人物評価が紹介されている。ハルが岩畔に対して親愛の情を持っていたのは確かなようである。
井川も、以下のようなハルの岩畔評を記している。
「当初、日本からコーネル(大佐)が来るというので大方、ビール腹の『体躯こそ堂々としているが余り中身は豊富で無い男』を想像していたが、実際にやって 来たのは『瀟酒たる映画俳優にでもありそうなタイプの美丈夫』であった。しかも、更に驚かされたのは、40そこそこのこの青年将校の博識と明噺さであっ た。それまでの、日本の外交官がちょっとしたことを尋ねてもすぐに本国に問い合わせると言って話が途切れてしまうのに対し、即座に明快な回答を与える岩畔 大佐は百人芸の持主であり、自分にこんな有能な部下がいたらさぞ助かることであろう」
ハルの知る日本の外交官と比べれば月とスッポンだったという訳である。
ハルは更にこうも言っている。
「近年日本の軍部が外交を引きずるという声をたびたび耳にするが、岩畔大佐の如き人材が多くそは、なるほど無理からぬ話である」
―日本人形・ハル子―
子供のいないハル夫妻に、岩畔たちは、持参した日本人形をハル子と名付けて贈った。
「ハルは春に通じ平和を意味します」
そんな井川のメッセージが付けられた贈り物を、ハル夫妻はいたく喜んで自分の寝室に飾ったという。
こうした、井川の社交センスは岩畔も大いに讃えているが、日本大使館員の間では、「何をへつらっているんだ」と評判は芳しくなく、井川への反発は更に高まったという。
しかし、考えてみれば人形を手土産にするという常識的な社交マナーも「へつらい」としか取れない連中が大使館員としてアメリカに駐在していたということである。
彼らの多くは戦後、政府に重用され、戦後日本の外交方針を決定したが、戦後になってからの方がいわゆる「へつらい外交」が多いというのは何を意味するのだろうか。
―バスに乗り遅れるな―
井川に対する大使館員たちの反感は、日米諒解案が表に出てから一層激しさをつのらせた。
日米諒解案を打電してしばらくすると、外務省は5万ドルの機密費を送ってきた。松岡がまだ帰国していない時点では、外務省も諒解案に前向きであったことが分かる。
しかし、この金が届くまで大使館員たちは、「本省はたいした関心を示さないであろう」と囁き合っていたというのだから、彼らの政治センスは皆無であった。
しかし、さしもの彼らも機密費が送られてくると事の重大性に気がついたようで、慌ててバスに飛び乗ろうとした。
彼らは岩畔に、「井川君のような民間人が日米交渉に参加することは好ましくない。従って本省が日米交渉を真面目に取り上げたこの機会に、井川君を交渉事務から除外してもらいたい」と申し入れた。
おとなしく帰るなら、送られて来た機密費から帰りの船賃を出してもいいというのである。
あまりの変わり身に呆れ果てた岩畔は、「今、漸く軌道に乗ろうとしている日米交渉の端緒は両牧師と井川君によって開かれたものである。今後も井川君がいな ければ円滑に進捗する見込みはない。この頃『バスに乗り遅れる』という言葉が流行しているが、私は貴殿達がバスに乗ることを拒否するものではないが、先に バスに乗っている人を引きずり降ろすことに同意し得ない。この件は私の判断によって決めることではなく、大使の裁断に困るのが妥当である」
と、野村に裁断を仰いだ。
野村の意見も、同じであることは言うまでもなかった。
野村としても、大使館にろくな人材がいない以上、井川には引き続き助けてもらわなければ困るのであった。
確かに、当時日本では「バスに乗り遅れるな」という言葉が流行っていた。
ナチスドイツのヨーロッパにおける快進撃を目の当たりにして、
「日本がぐずぐずしていれば、ヒトラーがヨーロッパを制圧してしまう。その後でドイツに接近したのでは肩身が狭い。今のうちにドイツを助けて参戦しておこう」
そんな強迫観念が日本を覆っていた。
日本にとって不幸なことに、最も強くその強迫観念を抱いていたのが外務大臣・松岡洋右であった。
ある時は、シンガポール、またある時はソ連と、松岡は日本の攻撃目標さえ支持し始めた。もちろん、ドイツの戦略に沿ってそのお先棒を担ぐためであった。
―忌避された若杉公使―
野村−ハル会談が始まると、それを支える事務レベルの折衝が必要ということになった。大使館の事務方官僚からの要望だった。井川と岩畔に対米交渉を独占された彼らとしても焦りが出てきたのであろう。
それももっともな話ということで、野村はハルに申し入れて、野村−ハル会談と並行して事務方の会合を設ける事になった。
会談は日本から、井川、岩畔、若杉公使、アメリカからはハミルトン極東部長、スミス日本課長、バレンタインが出席することになった。しかし、会談は最初から荒れ模様を呈した。
会談の冒頭、開会の辞をとうとうと述べた若杉公使にハミルトンらが猛反発したのである。
その場では、不愉快そうな顔をしただけであったが、翌日の野村−ハル会談で、ハルから、「若杉公使が会談をリードするような態度をとってハミルトンらを不快にした」と強硬な抗議が出た。
野村は若杉を会談のメンバーから外さざるを得なかった。
かくして、事務方会談の日本代表は再び岩畔、井川の2人だけとなった。岩畔はどこまで本気か分からないがその事に関して、
「それにしてもせっかく事務的会談に若杉公使が出席する事になり、我々も肩の荷をおろしたような安堵感を抱いたにも拘わらず、若杉公使が第1回会談で忌避せられた事は悲しいでき事であった」と記している。
―東京の諜者―
5月下旬、いつものようにハル邸を訪れた野村、井川、岩畔の3人の前に現れたハルはその表情も険しく、いつものにこやかさは微塵もなかった。
やがて、ハルが放った言葉は野村を仰天させた。
「東京からの情報で、日本政府は日米国交の打開に熱心ではないことが分かった。東京政府がこのままの態度を続けるようでは会談を続けても無駄である」
ハルの剣幕は尋常ではなく、その場の雰囲気は険悪になった。
これはまずいと思った岩畔は、「私はこれまでハル長官に対して自分の親に対するような気持ちで接してきました、それなのに今日の厳しい態度にはその意味が分からず戸惑っています」と、事の次第を明らかにするよう要求した。
親に対するような気持ちとまで言われたハルは多少顔を緩ませたという。気を落ち着かせたハルは事情を説明し始めた。
米国が東京に放ったスパイからの報告で、日本政府は「自衛権の解釈」「門戸開放」「機会均等」「日支事変終了後の駐兵問題」に関してアメリカ政府と根本的に異なる考えを持っているという事が分かったというのである。
「これは異なことを聞きます」
岩畔は直ちに反論に転じた。
「自衛権の解釈については我々がこの席で度々言明しているとおり日米の解釈に食い違いはありません。門戸開放や機会均等に関しては、日本は全く同意であ り、むしろその原則をなぜ中国だけに限るのか 『地球全表面にも公平に適用するべきではないか』 とまで思っています。『日支事変終了後の駐兵問題』に関 しても、日本政府は既に以前の主張から大幅に譲歩しており、今後の折衝次第で妥協点に達する事も決して夢ではないでしょう。以上より、日米交渉をここで破 談に導かなければならない理由は存在しません」
岩畔の説明が功を奏したのか、ハルはやがて機嫌をとり直し、その日もいつものように会談を始める事ができたという。
後になって分かった事であるが、この時期、ちょうど松岡から日米交渉に関する通報を受けた在日ドイツ大使館がドイツへその報告電を送り、ドイツにいる大島大使が松岡外相宛てにドイツの意向を打電していた。
ハルの立腹は、アメリカがそれらの電文を傍受して解説した結果だった。
岩畔に怒りの理由を尋ねられたものの、ハルは暗号を解読しているとも言えず、「謀者からの報告」と言ってしまったようである。
ハルとしては、松岡の面従腹背の裏切り行為に我慢ができなかったのであろう。既に松岡はアメリカにとって岩畔言うところの「悪魔大王」となっていた。
―ルーズベルトの招待―
岩畔、井川らのアメリカ滞在中、ウォーカー郵政長官は、彼らの変わらぬ相談相手となった。
ルーズベルトの、長年の選挙参謀だった彼は、大統領に自由に会う事ができ、野村−ハル会談が困難にぶつかる度、井川かドラウトがウォーカーの所に駆け込むのが常だった。まさに、大統領への直訴ルートでもあった。
5月末頃、ドラウトを通じて井川、岩畔の2人を大統領がニューヨークの私邸へ招待したいという話が持ち上がった。
2人は早速テーラーで白いタキシードを注文したが、岩畔は日米交渉成立の見込みがつくまで招待を延期してほしいと申し入れた。
その頃、岩畔はまだ遠からず交渉はまとまると考えていたようだ。
結果的に、岩畔、井川はアメリカ大統領との会見の機会を永遠に逃してしまうことになる。
「今にして思えば全く惜しい機会を失ったものである」
後年、岩畔は嘆いている。
この頃、ハルは病気療養を理由にウェストバージニアへ転地療養に出かけた。
野村−ハル会談はいったん中断である。
松岡が裏切り行為とも言える無礼かつ倣慢な態度に出てきた以上、米国首脳部としても日本にこれ以上譲歩することは危険と感じたようだった。
まして、国務省にはホーンペックをはじめとした対日強行派が控えており、その突き上げをくらう畏れも十分にあった。
イギリスに亡命したルドルフ・ヘスを聴取した英国政府を通じて、独ソ開戦が間近いという情報を仕入れていた米国としては、その情報の真偽が大きな関心の対象になっていた。
「倣慢な松岡が控える日本との交渉はひとまず棚上げして、独ソ戦が始まるかどうかを見極めてからでも遅くはない」
そんな考えがルーズベルトやハルにきざしたとしても不思議はない頃である。
米国にとって、今や、交渉を急ぐことにメリットは見出せなくなっていた。ハルが健康を害していたのは事実であろうが、様子見に転じるにはまさにピッタリのタイミングだった。
井川や岩畔にパーティーのお誘いがかかったのも、交渉は一旦「小休止」というような意味合いがあったのかもしれない。
―暗転―
6月21日、保養先のウェストバージニアからワシントンに帰ってきたハルから、野村に至急面会したいという要請が入った。
ワードマンパークホテルのハルの私室を訪れた野村、岩畔、井川の3人が通されたのは、ハルのベッドルームだった。
ハルはまだ病の床に臥せていた。
ベッドを囲んだ3人にハルは突然、「独ソ開戦に関する見通しはどうか」と問いかけてきた。
思っても見なかった質問に、野村は「的確な情報を入手していない」と答えるだけだった。
しかし、岩畔はハルの顔に明らかな失望の色が浮かんだのを見逃さなかった。
その後は、日米交渉のことが少し話題に出たもののその他にはこれといって急ぎの用件は無かった。ハルはその1件を訊くためだけに野村を呼んだのである。
その翌日、6月22日の夕刻、ハルの言葉が気になった野村は、大使館員と駐在武官を集めて、「独ソ開戦の見通し」を皆に問いかけた。
誰もが、それぞれの意見を述べたが「独ソ開戦必然論」を唱えたのは岩畔だけだった。中でもある情報担当秘書官に至っては、あらゆる論拠を挙げて「独ソ非戦論」を熱弁し、岩畔がそれに対して反論しても不愉快そうに自分の主張を繰り返すだけだった。
ところが、皆が解散して後、テレタイプ室に足を運んだ岩畔は、まさに「独ソ開戦」を伝える第一報が入電して来るのを目撃する。
強硬に独ソ非戦論を唱えていた秘書官のことを、「このときくらい他人の立場に同情した事はない」と岩畔は記している。
それにしても間抜けな話だった。既に独ソ戦が始まっているのも知らないで、ワシントンの日本大使館では皆が集まって、「独ソ戦ありやなしや」と議論していたのである。
岩畔は言う。
「それは迂闊(うかつ)を通りこした一幕の喜劇であった」
―米国のしっぺ返し―
独ソ開戦の、日米交渉に与える影響は甚大だった。
対ソ援助を準備し始めたアメリカは、日米交渉に対して洞ヶ峠を決め込んでしまった。
強力なドイツとの戦いに専念するための対日宥和である。ドイツがロシアで予想以上にてこずり消耗するようなら、アメリカにとって日米交渉は次第に意味のないものになっていく。
「独ソ戦の帰趨(きすう)を見定めてからでも遅くはない」
アメリカにとって、日本との交渉妥結を急ぐ理由は全く無くなってしまった。
6月21日、アメリカは、日本がアメリカに手交しそのままになっていた松岡案に対する回答を野村に手渡した。
その内容は、松岡に対するしっぺ返しであるかのように、日本に対して強硬なものに転じていた。
アメリカは自衛の見地から欧州大戦に参戦し得るが、日本はドイツに追随して参戦できないというような内容まで盛り込まれていた。
岩畔が盛り込んだ日本移民に対する差別撤廃の条項も削除されていた。
中国問題に関しても、日本が承認している汪兆銘政権ではなく蒋介石政権を中国政府として指定しており、解釈のしようによっては汪兆銘政権は否定されていた。
日米の交易も、とりあえず日中戦争以前の貿易量までの復活はうたわれていたが、それ以上のものに関しては更なる交渉が必要となっていた。
いずれにしても、今度は日本側が受け入れられなかった。
さらに、オーラルステートメントとして松岡に対するあからさまな意趣返しも盛り込まれていた。
オーラルステートメントは以下のようなものだった。
「国務長官は、日米両国のより良き理解をもたらし、太平洋の平和の確立のために、日本大使とそのアソシエイツ(井川と岩畔)によって成された真剣な努力を高く評価し、会談全体を通じて彼らを特徴づけた正直さをも評価する次第である」
と、井川、岩畔、野村の3人の努力を高く評価する一方で、松岡に対しては、
「政府の有力なる地位に有る日本の指導者が国家社会主義のドイツ及びその征服政策に抜き差しならざる誓約を与えている、そのような者が指導者として世論を動かしているようではいくら交渉しても実質的結果を収めることには幻滅を感じるだけである」
と断じていた。
アメリカは、無電傍受と暗号解読で松岡とヒトラーの間に存在する「抜き差しならざる」関係を知り尽くしていた。
岩畔の言葉を借りるならば、「松岡は既に悪魔列伝に加えられていた」のである。
一方、暗号が解読されていることにまで考えが回らない松岡は、アメリカの松岡に対する憎悪を野村や岩畔が自分の悪口を言っているためと誤解したようである。
松岡は野村に、
「岩畔、井川らは日米交渉に何等容喙(ようかい)すべき筋合いのものにあらず」として、交渉から両名を外すよう命じた。
ハルのオーラルステートメンツが、彼らのことをアソシエイツと呼び高く評価しているのが気にくわないというのである。
一方、その間、アメリカはひたすらソ連の善戦を願っていた。
独ソ戦が始まってしばらく経つと、それまで日本に好意的だったウォーカー郵政長官までが、「この戦争が長引くと面白いのだが」と洩らすようになっていた。
その頃岩畔は、井川や野村に対して今後の日米交渉の成り行きを予想している。
「米国は時間を稼ぐため日米交渉は依然継続するだろう。しかし、日米交渉が既に米国の時間を稼ぐ道具と化した以上、急速に成果を得る可能性は小さくなっ た。もし日本側が真剣に日米交渉を妥結に導こうとすれば、これまでの案より要求を下げなければならない。しかし、日本側としては無制限に要求を下げること は不可能であるから、交渉は長引き最後には決裂して戦争に突入する危険性も増すであろう」
その後の状況は岩畔の分析通り進んでいく。
交渉が暗礁に乗り上げてしまったところで、のちに岩畔豪雄が書いた『私が参加した日米交渉』と山川出版刊『井川忠雄日米交渉史料』の中から、彼らが見聞きした当時の米国の世情を紹介しておくことにしよう。
―米国国内にみなぎる反戦機運―
岩畔や井川が渡米した時、既に、米国首脳部は英国を支援するための対ドイツ参戦を決意していた。
米国の政治家たちにとって当時のヨーロッパの状況は、とうてい看過することはできなかったようである。
しかし、首脳部の思惑をよそに米国市民には厭戦思想が充満していた。米国を戦争に巻き込む怖れのあるコンボイ(対英援助物資を積んだ輸送船団を米国護衛艦 が随伴護衛するもの。もし、ドイツの攻撃を受け、応戦すれば米国は否応なく戦争に巻き込まれる可能性を蔵していた)や援英法案などに対して、リンドバーク をはじめとした著名人の反戦演説会が公然と開かれ、「徴兵につかまった」というような反戦映画も人気を集めていた。一般の米国人にとって「戦争は海の彼方 のでき事」であり巻き込まれるのは真っ平ご免という訳だった。
「対日世論を有利に導けば日米戦回避はそれほど困難ではない」
岩畔はそう考えていた。
―各国の策動―
米国に対する英国、ドイツを始めとする各国の働きかけは凄まじかった。
ドイツとしては、米国の欧州への介入は何とかして避けたい。
ルドルフ・ヘスのイギリス亡命と時を同じくして、メキシコ国境からはドイツスパイが米国に侵入、米国の戦争不介入と英独戦争に対する調停工作を試みている。
一方、それに対して英国は、ワイズマンらによる陰の工作とは別に前外相ハリファックスを米国に特派、米国の対独参戦を誘導するべく猛烈な政界工作を展開していた。
ドラウトやウォーカーのように英国に対して歴史的に悪感情を抱くアイルランド系米国人らは、ハリファックスを「ハリフォックス」と読み換え、
「米国人は狐にだまされるな」
と椰揄していたというが、国務長官ハルが自宅の棚に英国国王夫妻の写真を飾っていたのを見ても分かるように、大部分の古き良きアメリカ人は極めて親英的であった。
中国、蒋介石政権のアメリカへの働きかけも、特筆するべきものがあったという。古来、中国人は饗応、外交の術にはことのほか長けた民族である。
中国からは、多くのマスコミ人、文化人が渡米して、親中国世論の醸成に大わらわであった。
また、蒋介石夫人・宋美齢も度々訪米し、艶然たる美貌をもってアメリカ朝野の人気を独占していた。
議会には、既に強力なチャイナ・ロビーができあがっていた。
議会だけではない。国務省にも外交顧問ホーンペックを始めとした強力な親中国人脈が形成されていた。
かくして、アメリカからは大量の援助物資が援薄ルートを通じて中国へ流れ込んでいた。
一方、それに対して日本の外交は全く不在と言っても良かった。
そうした状況に危機感を覚えた岩畔は、武藤宛の電報で日米諒解が成立してからのこととして、対米外交方針は大幅に変えなければならないことを提言している。
「対米工作ノ重点ヲ平和空気ノ醸成二指向スルコト」
「之ガ為ニハ相当経費ヲ要スベシ」
これらの言葉から岩畔の危機感と並々ならぬ決意が窺える。
こうした岩畔の電報であるが、外交電と同様、米国に解読されていたかと言うとそうでもなかった。外務省暗号、海軍暗号は既に米国に解読されていたが、唯 一、陸軍の暗号だけは、この時も暗号として機能していた。まさに岩畔が整備してきた諜報システムの勝利と言えた。
―国論を統一したルーズベルト―
岩畔は、ルーズベルトの巧みな政局運営を高く評価している。
岩畔から見て、国論の統一に関するルーズベルトの手腕は天才的だったという。
新聞記者にあだ名で呼びかけマスコミと良好な関係を維持し、時には最初につまらない雑談をしておいて記者たちが今日は大したニュースが無いと思って帰りか けると、おもむろに懐から重大ニュースのメモを取り出して読み上げるといった術策を弄したという。つまらないニュースだからと言って記者たちは安心して席 を外すことができなくなる、と岩畔は感心している。
アドバルンの揚げ方もまた巧みであり、特定の計画や政見を故意にリークし世論の反応を見たかと思えば、米国の世論がコンボイ、援英法に集中しているすきに乗じて密かにソ連と協定を結ぶなど神出鬼没の政略を駆使したという。
「デモクラシー政治下に於いて戦争に突入することは特に困難であるが、自衛権の侵害も対する防衛戦争だけは例外に属する」
と岩畔も書いているように、既に、米国は自衛を大義名分として対独参戦することを考えており、そのための用意として、日本に対しても自衛権の拡張解釈を要求することを忘れなかったのである。
一方、アメリカは着々と戦争準備を整えていた。
岩畔や井川、野村らが、休日に郊外にドライブした時など、しばしば森林を伐採しての大規模な整地工事にぶつかったが、それらは兵舎や飛行場の建設工事だったという。
「日本では、日本の為にならない外国の英雄でも、英雄は英雄として推賞せられるのを常としたが、米国では自国のためにならない外国の英雄は悪魔扱いされたようである」
岩畔にとって、蒋介石が記録映画で出て来ると万雷の拍手でこれを迎え、一方ドイツではいまだに英雄であり国家元首であるヒトラーをへル・ヒトラー(地獄のヒトラー)と椰揄するアメリカ人のドラスティックな感覚は、きわめて印象深かったようである。