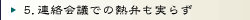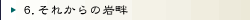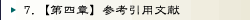4. 失われた最後のチャンス
―ワシントンを発ち、日本へ―
交渉に行き詰まりを感じた岩畔がワシントンを後にしたのは、昭和16年7月31日のことだった。
「日米交渉に対する認識に於いて東京と出先との間に大きな食い違いが生じたからこれを調整する必要が生じた」
というのも一つの理由だったが、今となっては一刻も早く、
「独ソ戦開始とともにその性格を変えつつある日米交渉の真相を、本国政府に説明する必要があった」
というのが主目的だった。
日本政府には、独ソ戦開始後、世界に重大な変化が生じたことを理解している者はほとんどいなかった。
放っておけば、強硬になった米国の態度と遅々として進まぬ交渉にしびれを切らして、主戦派が台頭してくることは目に見えていた。
―スチュワーデスの配慮―
7月31日、岩畔と、井川はワシントンを後にした。
日本軍が南部仏印に進駐したのはその5日前のことだった。アメリカは直ちに対抗措置として在米日本資産の凍結を行っていた。
対日世論がますます悪化する中、日本人2人だけの旅行を心配したドラウトがサンフランシスコまでつき添った。
途中、乗り継ぎに立ち寄ったピッツバーグ飛行場で、ドラウトはそこまで乗ってきた飛行機でスチュワーデスに聞いたという話を2人に始めた。
ワシントンで積み込まれた新聞に、日本軍の南部仏印進駐に対する激烈な批判記事が載っていた。気の毒に思ったスチュワーデスは、岩畔、井川がピッツバーグで降りるまで新聞を配るのを控えていたというのである。
改めて日米関係の厳しさを感じるとともに、スチュワーデスの配慮に感謝した井川と岩畔は、航空会社の社長宛にその場で感謝の手紙を書いた。
気のいい「謀略家」たちではあった。
―主戦論一色に―
2週間の航海を終え、帰り着いた日本は、既に数ヵ月前に岩畔らが後にしたのとはまるで別の国になっていた。
渡米の際に彼に託された日米国交回復への期待や祈りは今や影も形も残ってはいなかった。
新聞紙面は主戦論で埋め尽くされ、道行く人々の顔さえ、せまり来る戦争を前にこわばっているかに見えた。
「何事かを思い詰めた処女が、今にも川の中に飛び込もうとして、じっと水面を見つめているような(風情が漂っていた)」
と岩畔は記している。
「何事によらず、日本人は深刻に考え過ぎ悲壮感に浸る傾向をもっているが、昭和16年8月頃に於ける日本人の大部分はこの傾向の虜(とりこ)になっていた」
しかし、無為に過ごす時間は残されていなかった。何としてでも、この流れを変えなくてならない。
近衛総理、外務省、陸軍省、参謀本部、海軍省、海軍軍令部、宮内省。日本を動かすありとあらゆる力の源に、岩畔は自ら足を運んだ。
「日米の間には、鉄鋼1対20、石油産出カ1対数百、石炭1対10、電力1対6、アルミ1対6、飛行機1対5、自動車1対50、船舶保有量1対2、工業労 働力1対5といった格差があり、晶眉目に見ても、物質戦力比はアメリカの10分の1以上もない」
これらの数字は、岩畔が渡米する時、龍田丸で一緒になった新庄主計大佐の報告書によるものだった。
新庄大佐も、東条に左遷されて涙の日々を過ごしていたわけではなかった。
岩畔の主張は簡単だった。アメリカの国力を相手に、日本が勝利する見こみは万に一つも無い。日米交渉は、続行するべきである。他に日本の選択の余地は無い。
しかし、時、既に遅かった。
これほど単純な詰も、今や人々の理解を得ることはできなかった。
戦機は既に動き始めていた。
―近衛首相―
近衛首相は、日米国交修復に未だ望みを失っていなかった。
「日米交渉には勇気を倍化して立ち向かう」
と、いちおう決意だけは力強かった。
「日米諒解案」が日本で巻き起こした「騒動」の顛末と、その時の松岡の対応を近衛の口から聞いた岩畔は、松岡の横暴に憤るとともに、近衛が総理大臣として の権限を発動して、承認してくれさえすれば良かったのにと、いまさらながら恨めしい気持ちを禁じ得なかった。
「岩畔は自分の子分だったのに裏切った」
と、松岡が公言していたと聞くに及んでは、怒りのあまり、
「今から松岡邸に行って話をつけましょう」
とまで言いつのる岩畔だったが、
「今の松岡君は正常な神経では無いから」
と近衛の制止を受けている。
「日米国交を修復するには南部仏印から撤収する以外ない」
と、意見を具申した岩畔に対して、
「自分も同意見であるが、陸軍が聞かないだろう」
近衛に現実の枠組みから足を踏み出そうという覇気は見られなかった。
近衛に、これ以上のリーダーシップを期待することは無理であった。
―陸軍省―
*東条英機
8月16日、岩畔は東条陸相を官邸に訪ねた。
日米交渉の実態を報告するためだった。
案の定、東条はさほどの関心も示さなかった。
所詮、東条にとって米国に岩畔を派遣したのもただの左遷に過ぎなかった。
「日米諒解案」に日本が沸いた時は、「どうせ岩畔の大風呂敷だろう」と言いながらも、陸軍としては支持する方針を打ち出した東条であったが、話が流れた今となっては、岩畔の言葉に耳を傾けるつもりはなかった。
*武藤章
軍務局長・武藤章は東条と違っていた。
中国大陸への進出を積極的に推進した武藤だったが、それだけに、泥沼と化した現状に自責の念も強かったのであろう。
彼は中国問題と日米国交を一挙に解決しうる日米交渉に、終始積極的であった。
岩畔のアメリカ派遣の裏には、彼の強い意志が働いていたのではないかとさえ言われている。
「ルーズベルト、近衛の首脳会談が開かれる時には、陸軍の政治スタッフとして随行する」
彼はいまだに交渉の敗北を認めてはいなかった。
しかし、陸軍に於いても大勢は武藤や岩畔の思惑と反対の方向に動いていた。
既に、陸軍省の中で、岩畔を見る目は厳しかった。
陸軍にとって、もはや、アメリカは「敵国」であり、岩畔は親米派として警戒しなければならない相手となっていた。
「陸軍部内では親米的な言動はしない方がいい」
後任の軍事課長、真田大佐の耳打ちがすべてを語っていた。
―参謀本部―
岩畔はそれでも、諦める訳にはいかなかった。今度は、参謀本部を訪れた岩畔は、参謀総長以下すべての参謀を集めて講演会を行った。
しかし、今や南方作戦に熱中する幕僚たちに対米交渉などはあまり眼中になかった。
「もはや日米戦は必至である」
そう断言した課長もいた。
「ならば訊くが勝つ見込みは有るのか」
「勝つ負けるの問題ではない」
問答無用という訳である。これ以上何を言っても無駄であった。
―海軍省―
陸軍がだめなら、海軍が頼りとなった。
岩畔としては、対米戦に慎重であると聞かされていた海軍に期待するところは大きかった。
彼はここでも、海軍大臣、軍令部総長、海軍省の部局長約30名を集めると、帰朝報告会を行った。
しかし、彼の期待はここでも見事に裏切られた。
講演が終わるや否や、こんな質問が発せられた。
「今やABCDラインは着々と進められ、ほとんど完成に近づいている。この状況下において時間を無為に過ごすことは自滅を待つに等しい。この情勢を打開する唯一の道は、対英米戦争決行より外にないと信ずるが貴見はどうか」
それはもはや質問ではなかった。
これでは陸軍と同じである。
「それでもまだ日米交渉は継続すべきである」
岩畔の答えはそれだけだった。
対英米戦となれば、とたんに海軍の出番である。既に、彼らのかかとも地面をまともに踏んではいなかった。
―外務省―
豊田外相、天羽次官、寺崎アメリカ局長の3人と面会している。
しかし、ここでも「糠に釘」だった。
―宮内省―
木戸内相、松平宮相、鈴木侍従長、蓮沼侍従武官長らと面会。
ここで初めて、岩畔は話を熱心に聞いてもらえた。
日米父渉の継続にも、一同が賛同してくれた。
「四方(よも)の海みな同胞(はらから)と思う世になど波風の立ちさわぐらむ」
と詠まれた明治天皇の心は、生きていた。
岩畔が宮内省を訪れた裏には、心中秘かに期待するところがあった。
しかし、岩畔の「謀略」は洩れた。侍従武官の1人が通報したのである。
翌日、参謀本部は岩畔に今後一切の宮中への参内を禁止した。
「親米的な意見も口に出すな」
まさに、だめ押しだった。
―3つの方策―
岩畔は、ただ単に「平和の維持」を説いて回っただけではなかった。日本に残された具体的な方策を彼は提示した。
彼は三つの選択肢を提示し、それぞれの得失を説いた。
以下にその3つを引用する。(※9)
・第1案 対米開戦
日米の戦力は余りにも隔絶しすぎ、現状に照らし必敗の公算が大である。
しかし、アメリカの戦争準備はまだ完成していない。虚をつけば、太平洋上の海戦に於いて一時的勝利を得ることは可能であろう。
しかし、米国を全面的に屈服せしめる最後の決め手を持たない日本は、仮に先制攻撃をかけ、マレー、スマトラ、フィリピンなどを奪取することができたとしても、昭和17年夏以降になれば強力な米軍の反攻が始まり、奪取した地域を確保することも困難になろう。
本案(対米開戦)をとる場合には、先制攻撃の計画よりも、両3年後の情勢に処し、勝利を得る確信の有無が重要な鍵になるが、その確信は誰にもあるまい。
だから、第1案を強行することは避くべきである。
・第2案 日米国交回復
日本にとって最も好ましい案であるが、我々に有利な条件で日米国交を修復し得たのは独ソ開戦以前のことである。
今日我々が日米国交修復を強行しようとすれば、仏印からの全面撤兵と日支事変終了後支那からの全面撤兵を甘受する必要があろう。
しかし、アメリカへの譲歩は米国側を増長せしめ、日米国交回復、米国の欧州戦争参加、独伊屈服、日本孤立となる可能性が有る。
この案を進めるに於いては全国力をあげて軍備を充実することと巧妙な外交施策を採ることが不可欠である。
・第3案 情勢観望(日和見)論
戦備を整えつつ形勢を観望しようとする案である。
しかし、この案では、既に盛り上がっている主戦論に対抗することはできない可能性が高い。
もしこの案を強行すれば五・一五事件又は二・二六事件に似てそれよりも遥かに規模の大きいクーデターないし内乱が起り、主戦派の内閣が出現し対米戦争への突入が行われる公算が大である。
当時は第2案が最良であると確信していた岩畔だったが、後年になって、第3案でも良かったのではないかと記述している。もし、ドイツのスターリングラードにおける大敗走まで情勢を観望していれば、主戦派もその影を潜めていったのではないかというのである。